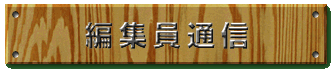
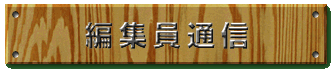
藤沢師の新たな挑戦を待望する
| 第59回桜花賞は、新進気鋭の福永祐一に導かれたプリモディーネの快勝で終わった。 戦前における勝ち馬検討の焦点になったのは、98年の年度代表3歳牝馬スティンガーの扱いであったろうことは衆目の一致するところ。60年近い桜花賞の歴史の中で、年が明けてから1度もレースに使わず、いわゆるぶっつけ本番で臨んで勝った馬は1頭もいなかった。藤沢和師は、敢えてタブーに挑んできたわけだ。 もし、こうしたローテーションで来て勝つようなことになれば、永年根付いてきていた、こと桜花賞に関する限りでの臨戦過程についての厩舎関係者の考え方を根底から覆すことになる。 囲碁や将棋の世界では定石と言うものがある。しかし、一方で「名人に定石なし」という俗諺もある。レースに出走させるにあたって、“こうでなくてはならない”ものがあって当然ながら、そうしたことに囚われない自由な考え方、やり方もあって良いだろう。 勝てば官軍、正当性を認めさせるにはとにかく勝つことだ。決して易しくはないものの、後進に道をつける先達を務められる数少ない人の1人だ。先へ進む為にも、これに懲りず機会があれば引き続き古い殻を破ることへの試みを、是非続けて欲しいものである。
|
![]()
(C) 1999 NEC Interchannel,Ltd./ケイバブック